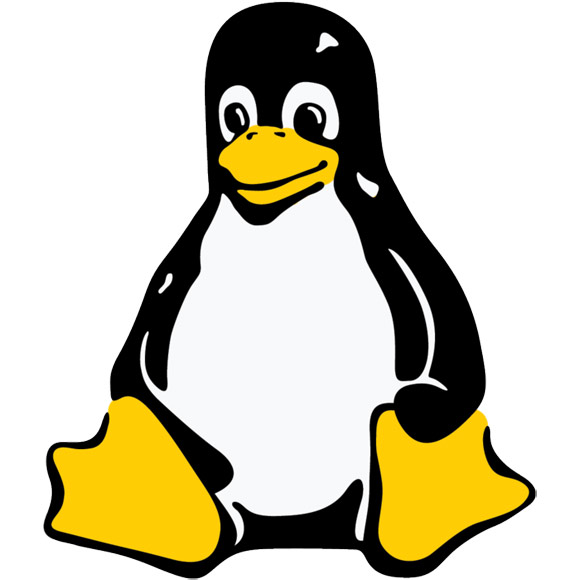第4世代
-

Multics は1970年代の様々なOS、特にUNIXに影響を与えた。
もうひとつのミニコンピュータ用OSとしてVMSが有名である。
初期のマイクロコンピュータはメインフレームやミニコンピュータのような精巧なOSを必要としていなかったし、それを搭載するだけの容量もなかった。
そこで、必要最小限のOSが開発された。
初期の特筆すべきOSとしてCP/Mがある。
これは8ビットのマイクロコンピュータではよく使われた。
その大雑把なクローンとしてIBM PC用にPC DOSが生まれ、そのOEM版であるMS-DOSが広く使われるようになった。
MS-DOSの後継OSによってマイクロソフトは世界有数のソフトウェア企業となった。
1980年代の他の流れとして、アップルコンピュータのMac OSがある。
第5世代
-

1990年代までにパーソナルコンピュータのような小型のコンピュータの性能が向上し、拡張性の高いGUIとともに、メインフレーム用途のような、より大きなコンピュータ向けのOSが備える堅牢性と柔軟性が求められるようになっていた。
1987年にIBMとマイクロソフトが、プリエンプティブ・マルチタスクなどを実装したパソコン向けOS、OS/2を発表した(GUIは同年の1.1より。
ネットワーク機能は拡張版で搭載)。
1988年に登場したNEXTSTEPは、業務用途に耐える堅牢性とオブジェクト指向による柔軟性、高度なグラフィックス機能と一貫したGUIといった新世代のデスクトップOSで求められる機能を全て実現した。
1994年にマイクロソフトが発表したWindows NTは、1999年以降にはマイクロソフト社の全OS製品のベースとなった。
アップルは2001年、NEXTSTEPを発展させたUNIXベースのMac OS Xを新たにリリースした。
これらはいずれもGUIや堅牢なマルチタスク(プリエンプティブ・マルチタスク)を備えており、オープンで低価格な分散コンピューティングを広めたが、信頼性・可用性を重視する用途には現在でもメインフレームも使用され続けている。
オープンソースの流れでは、GNUがUNIX向けのツール群を開発し、これらをLinuxカーネルと組み合わせたOSとしてのLinuxはUNIX系OSの主流となった。
BSD系OSもUNIX系OSのシェアの一部を占めている。
また組み込みシステムにもより複雑な機能が求められるようになり、汎用OSをベースとした組み込みオペレーティングシステムの利用が盛んになっている。